
意味と改善する方法が知りたい。
こんな悩みにお答えします。
本記事の内容
- 冗長表現とは
- 冗長表現のパターン
- 冗長表現の改善方法
結論からいうと、冗長表現とは、読者にとって読みにくい文章です。
無駄に長い文章や、専門用語が多く、理解しづらい文章も、冗長表現に当てはまります。
この記事を書いている僕も、冗長表現に悩んでいました。

本記事では、よくやってしまう冗長表現の種類と、改善方法を、例をもとに解説していきます。
「あ、自分の文章が当てはまっている」なんて思うかも知れませんが、失敗に 気付くのは改善するチャンスです。
ではでは、サクッとやっていきましょう。
冗長表現とは
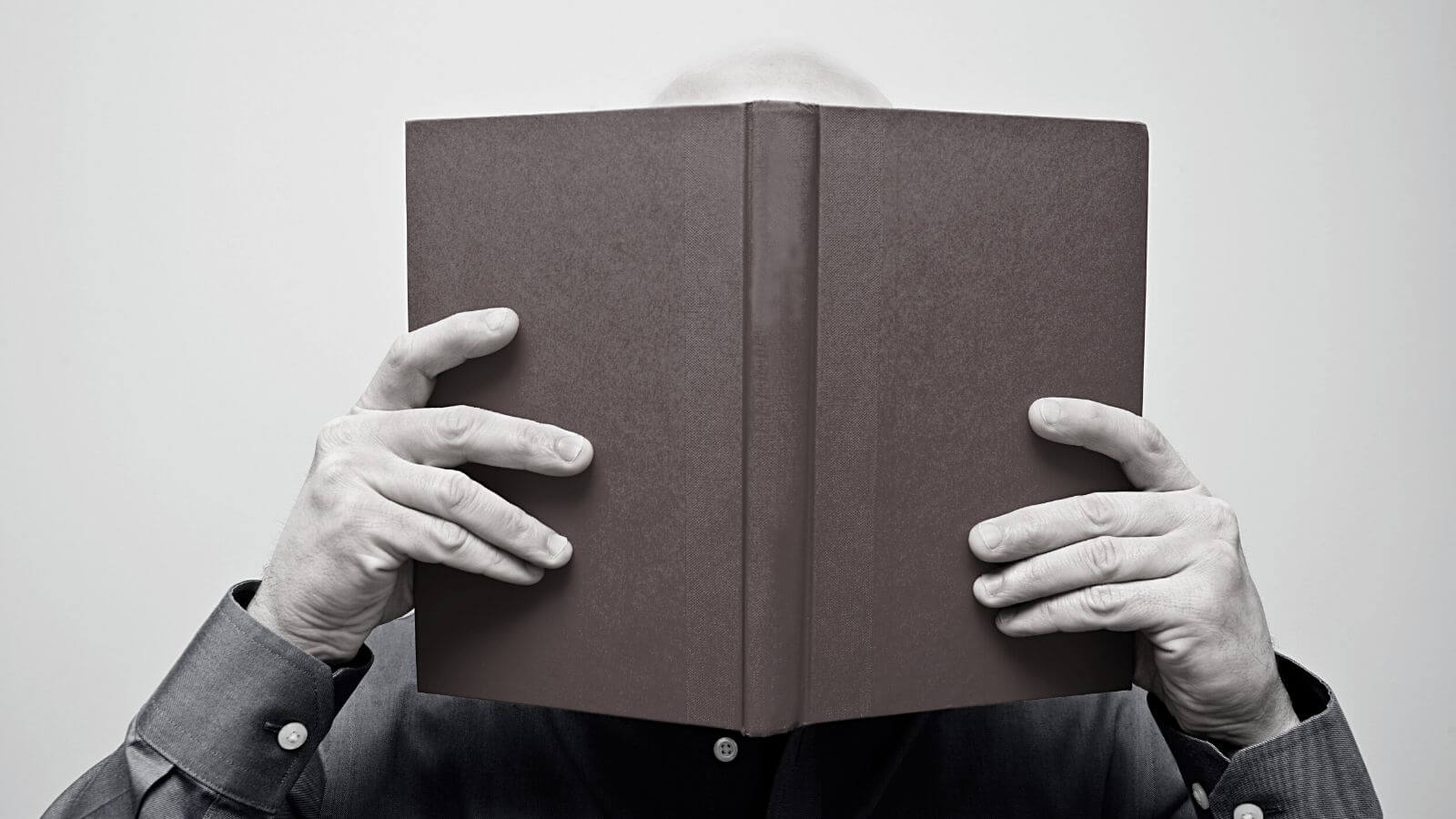
冗長表現とは、読みづらい文章、と理解すればオッケーです。

まずは、よくある冗長表現を確認しましょう。
ポイント
- 一文が長くなっている
- 「〜で」「〜が」で文章を繋げすぎている
- 話が脱線している
- 「〜することができる」などの冗長な文末になっている
- 二重敬語になっている
- 二重否定になっている
- 難しい文章になっている
上記が、よくある冗長表現になります。文字数を増やそうとして言葉を詰め込みすぎると、十中八九、冗長な表現になるんですよね。
読者にとって読みやすい文章は、無駄のない文章です。無駄な言葉を削り、読み手に優しい文章を作成していきましょう。
余計な単語が多く、一文が長い

- 接続詞を削る
- 類義重複を削る
- 「〜という」を削る
- 修飾語を削る
- 「〜で、〜が』で文書を繋げすぎない
冗長表現をかわす方法は、伝えたい内容をシンプルにすることです。
一文にあれこれ注ぎ込まず、とにかくシンプルに文章を書けば、冗長表現は防げます。
文章の書き方の基本は、一文一義です。

一文一義については、一文一義の本当の意味と使い方を解説【文章が苦手は終わりです】で詳しく解説しています。
-
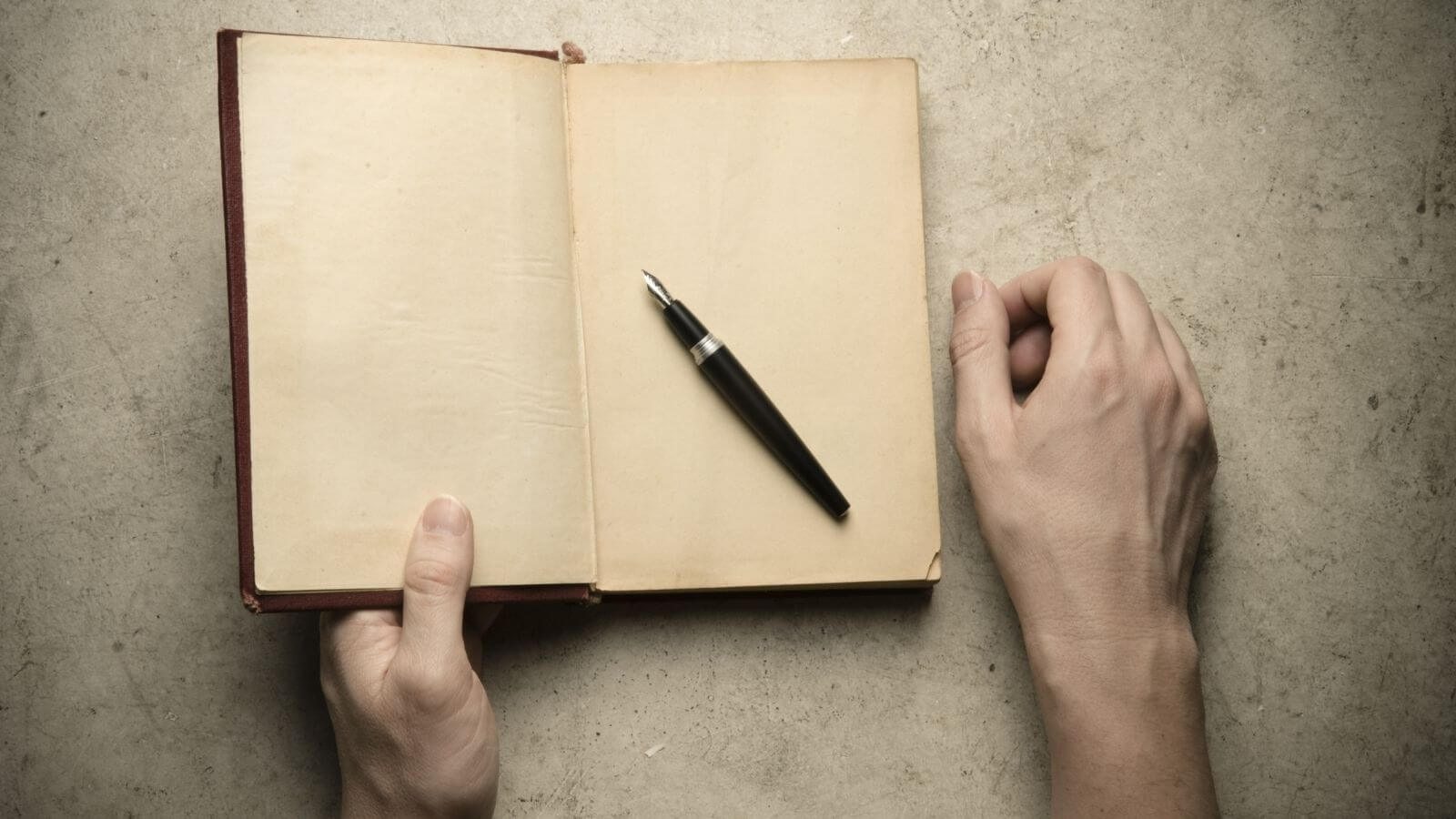
-
一文一義の意味とは?正しい使い方を解説【読みやすい文章の書き方】
一文一義について解説しています。一文一義とは、一文を短くして読み手に理解しやすい文書を書くスキルです。文章を書くのが苦手な人や、一文一義の応用する方法を知りたい方におすすめの記事になります。
続きを見る
接続詞を削る
接続詞を使いすぎると、読書に読みづらい文章になります。

例文
Aというアイドルグループは20代前半の男性で構成された男性アイドルグループです。そして、Aの新曲は、多くの人を感動させている。
↓
Aは20代前半の男性で構成されたアイドルグループです。Aの新曲は、新曲は多くの人を感動させている。
接続詞「そして」を削りましたが意味は伝わります。
接続詞を使わなくても意味が伝わる場合は、外してオッケーです。
類義重複を削る
類義重複とは、一文に同じ意味の単語が何度も使われることです。
先ほどの例文をみてみます。
例文
Aというアイドルグループは20代前半の男性で構成された男性アイドルグループです。そして、Aの新曲は、多くの人を感動させている。
↓
Aは20代前半の男性で構成されたアイドルグループです。Aの新曲は、新曲は多くの人を感動させている。
アイドルグループの単語が重複していたので、一文にまとめました。
一文に同じ単語が重複していると、かなり読みづらい文章になります。
別の例を挙げてみます。
例文
帰宅中の帰り道
↓
仕事の帰り道に

例文
まず最初に
↓
まずは〜
最初に〜
「まず」と「最初」は同じ意味です。普段の会話では、まず最初に〜などが使われますが、文章では使わないようにしましょう。
「〜という」を削る
内容説明する「〜という」は、文章を柔らかくする効果があり、多用する人が多いです。
しかし多くの場合「〜という」は削って問題ありません。
例文
Aというアイドルグループは20代前半の男性で構成された男性アイドルグループです。
↓
Aは20代前半の男性で構成されたアイドルグループです。Aの新曲は、新曲は多くの人を感動させている。
「という」の文章を削り、スマートな文章になりました。
文章があまりにも固い場合に限り「という」を使うケースもありますが、基本的には削って問題なし。
修飾語を削る
修飾語とは、文章を彩る言葉です。
小説など物語を書く際には、読者に描写をイメージしてもらうために使われます。

例文
とても綺麗な女性
↓
綺麗な女性
「とても」を削り、文章をスマートにしました。
「綺麗な女性」を強調しする場合は、「とても」を加えて問題ありません。
必要か不要かは、記事の雰囲気を見て判断しましょう。

「〜で、〜が」で文章を繋げすぎない
「〜で、〜が」は、曖昧な文章をつなぐ、便利な接続助詞です。
使い勝手が良い反面、多用して読みにくい文章に仕上がっているケースがあります。
例文
今日は暑いので、待っているのも辛かったが、近くにコンビニがあったので、中で待つことにした。
↓
今日は暑くて、待っているのも辛い。近くにコンビニがあったのから、中で待つことにした。
一文を短くして、視覚的に理解しやすい文章になりました。
接続助詞を多用すると、何を伝えたいのか、読者には分かりません。
「〜で、〜が」を使う場合は、冗長な文章になっていないか確認してください。

余計なことを伝えて、話が脱線している

- 「ちなみに、余談ですが」は使わない
- 逆説ではない「が」は省く
内容を詰め込みすぎて、記事の内容が脱線しているケースが多くあります。
読者はタイトルに合った内容を知りたいんですよね。
良かれと思い、関係のない話をするのは、冗長な文章になります。
「ちなみに、余談ですが」は使わない
ブログなどでよく見られる冗長表現です。
例文
見出しが「文章の書き方」に対し
「余談ですが、子供が生まれました」
上記のように書かれていると、意味不明ですよね。
余談とは、本質からはずれた話を意味します。
伝えたい内容以外は、文章に詰め込まないようにしましょう。

逆説ではない「が」は省く
逆説ではない「が」は、省いて問題ない場合がほとんです。
例文
私事で恐縮ですが、相談があります
↓
相談があります
「私事で恐縮ですが」は、目上の人にお伺いを立てる場合に使う言葉です。

逆説の意味を持たない「が」を省いても、文章の意味は変わりません。文章をスマートにするために、不要な言葉は削りましょう。
「〜することができる』などの冗長表現は避ける

「〜することができる、」などの文章は、説得力に欠ける文章になります。
例文
私は料理をすることができる
↓
私は料理ができる
言い切る文末にして、文章に説得力が出ました。
「〜することができる」などの冗長表現になる場合は、言い切る文章に変更しましょう。
「〜することができる」は、間違った日本語ではありません。
文章を柔らかくする効果があるので、場合によっては使ってもOKです。
しかし使いすぎると、幼稚なイメージや説得力のない文章になるので、注意が必要。
二重敬語は使わない

二重敬語とは、同じ種類の敬語に、さらに敬語を重ねる文章です。

例文
させていただきます
↓
〜いたします
伺わせていただきます
↓
伺います
拝見させていただきました
↓
拝見しました
二重敬語はビジネスシーンでも誤って使われている場合があります。

二重否定の使い方には注意する
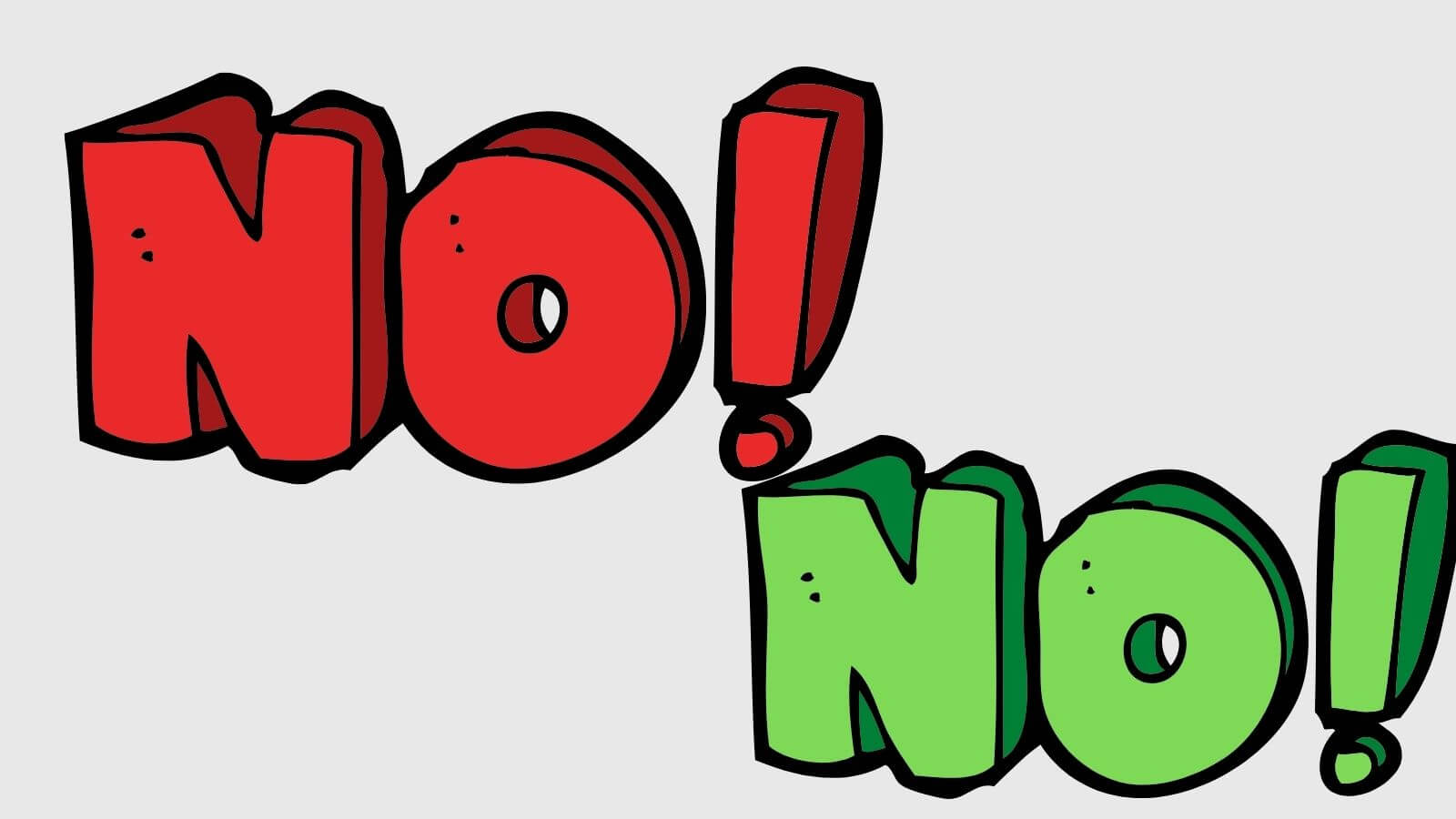
二重否定とは、否定の意味をもつ言葉を重ねる文章です。
二重否定を使えば、より肯定的な文章を作れますが、間違えた使い方をすると、周りくどい印象になります。
例文
私は文章が書けないわけではない
↓
私は文章が書ける
上記の例文は、「書けない」と「わけではない」が同じ意味になります。
文章としても、かなり周りくどい感じがします。

次に、強い肯定感を出す二重否定の使い方の例を紹介します。
例文
この記事を読めば成功しないはずはない。
「しない」「はずはない」の二重否定ですが、文章の意味は、「成功する」です。
強い肯定感を伝えたい場合は、二重否定を使ってもOK。
しかし難しいスキルなので、慣れないうちは使わない方がいいですね。
難しい文章にしない

- 専門用語は言い換える
- 誰に向けた文章なのか明確にする
専門用語を使う文章は、読者にとっては負担が大きいです。
理解できない単語が出てきたら、読者はその場で離脱します。

論文のような学術系文書ではない場合、読者に寄り添った文章を意識しましょう。
専門用語は言い換える
専門用語を連発する記事を、好んで読みたい人は少ないです。

例文
コンシューマー
↓
消費者
この記事の執筆、ASAPでお願い
↓
急いで、この記事を執筆して
マーケティング用語、ビジネス用語などは理解できない人が多いので、なるべく言い換えましょう。

誰に向けた文章なのか明確にする
ペルソナをはっきりする、ともいわれます。
同業者に書く記事なら、専門用語を使ってもオッケーです。
しかし初心者に向けて書く記事の場合、専門用語は理解できず、冗長な表現になります。
記事を執筆する際は、誰に向けて、何を伝えるか、書く前に決めておきましょう。
こそあど言葉の使い方を間違えない

こそあど言葉とは、「これ、それ、あれ、どれ」を使って、何かを指し示す言葉のことです。
会話でよく使われますが、文章にすると何を指しているかわからず、読者を混乱させてします可能性があります。
例文
僕は毎日、筋トレをすると決めました。それは健康のためです。しかし怠け者の僕は、その習慣を続ける自信がありません。
↓
僕は毎日、筋トレをすると決めました。理由は健康のためです。しかし怠け者の僕は、筋トレの習慣を続ける自信がありません。
こそあど言葉は、次に続く言葉が何を指しているのかを説明するため、使い方によっては読者の理解を助けてくれます。
ただし使い過ぎると混乱させてしまう可能性もあるため、多用していないか確認しましょう。
冗長表現の削りすぎにも注意

冗長表現は、基本的には削るべきです。しかし、全て削る必要はありません。
なぜなら、冗長表現の全くない文章は淡々とした文面になり、読者の感情に刺さらないからです。
冗長表現は、文章の脂肪といわれます。そのため、一気に削ぎ落とすべきと考える人は多くみられます。
しかし、文章も人と考えてみると、どうでしょうか。体脂肪率0%の人間は存在しません。
とはいえ、体脂肪率50%以上だと、健康的に問題が発生しますよね。
つまり、適度な体脂肪率を作ることが大切です。冗長表現を使える割合の決まりはありません。
そのため、文章の世界観に合わせる必要がるでしょう。
注意して頂きたいのは、冗長表現は全て削る必要はないということです。
ガリガリになりすぎず、太りすぎずのラインを見極めましょう。
まとめ:冗長表現とは、読者に読みづらい文章

本記事をまとめます。
- 冗長表現とは、読みづらい文章
- スマートな文章を意識する
- 一文一義を意識する
文字数を稼ごうとして、言葉を詰め込みすぎると冗長表現になる場合が多いので注意してください。
冗長表現にならないコツは、伝えたい内容を明確にして、シンプルに届けることです。
あれこれ言葉を詰め込みすぎると、読み手には負担がかかります。
ブログを書く人や、記事を書く人は意識してください。
ではでは。
